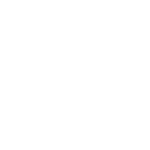「アクセスはあるのに、問い合わせが増えない」──その原因は“思い込み”かもしれません
中小企業のホームページを見ていて、よく感じることがあります。
それは「自分たちの理想で作られていて、ユーザーの視点が抜け落ちている」ということ。
実際、アクセス数が一定以上あるのに、問い合わせ(コンバージョン=CV)率が伸びないサイトは少なくありません。
その多くは、デザインや情報量の問題ではなく、「サイト設計の考え方そのもの」にズレがあるケースです。
この記事では、**中小企業のホームページで成果を下げている“3つの思い込み”**を解きほぐし、具体的な改善の方向性を解説します。
—
思い込み①:「うちの強みを全部載せれば、信頼される」
情報を増やす=信頼を得る、ではない
企業サイトでよく見かけるのが、「自社紹介が長い」「メニューが多すぎる」という構成です。
しかしユーザーは、最初から会社の全てを知りたいわけではありません。
むしろ「今、知りたい情報」にすぐ辿り着けないと、離脱の原因になります。
総務省の調査(※1)でも、Webサイト離脱理由の上位には「情報が多すぎて探しづらい」「目的の情報に辿り着けない」が挙がっています。
つまり、「情報量=信頼」ではなく、「整理されている=信頼」です。
- まず1ページ1目的を意識する(例:製品紹介ページなら“問い合わせにつなげる”)
- 会社紹介や沿革は、興味を持った人が後から見る構成にする
- 見出しで“要点”をすぐ把握できるようにする
こうした“情報の引き算”が、実は信頼感を高める近道になります。
※1 出典:総務省「情報通信白書 2024」より
—
思い込み②:「デザインをオシャレにすれば成果が上がる」
見た目より“伝わりやすさ”が先
デザインを整えること自体は大切です。
ただし「見た目を良くする=成果が上がる」ではありません。
ユーザーはデザインの美しさよりも、「この会社は自分の課題を解決してくれそうか」を見ています。
つまり、“第一印象”ではなく“第一理解”が重要です。
- キャッチコピーで「誰に」「何を」「どう良くするか」を明確にする
- 写真・ビジュアルは「実績」「スタッフ」「現場感」など“リアルさ”を重視
- デザインよりも「スマホでの見やすさ」「読みやすい行間・余白」を優先
オフィス・ヒロの制作事例でも、トップビジュアルの見せ方を少し変えただけで
問い合わせ率が約1.8倍になったケースがあります。
「オシャレ」より「伝わる」──これが成果を上げるサイト共通の特徴です。
—
思い込み③:「問い合わせフォームがあれば十分」
“行動を促す導線”がなければ、誰も動かない
「問い合わせはこちら」のボタンを設置しても、クリックされないページは多いもの。
なぜか? それは、“行動する理由”が示されていないからです。
ユーザーは「この先で何が得られるのか」を納得できたときに、初めて行動します。
つまり、**行動を促す“導線設計”**が成果を分けます。
- ボタンの上に「こんな方はぜひご相談を」と書く
- CTAの位置はページ末だけでなく、途中にも設置する
- フォームの入力項目は必要最低限にする(離脱率を下げる)
Googleが公表している調査(Think with Google, 2023)によると、
フォーム改善でCVRが平均20〜30%向上した事例もあります。
問い合わせボタンは「飾り」ではなく、「行動のスイッチ」です。
—
まとめ:思い込みを捨て、“数字”で判断する
ホームページ改善において一番大切なのは、**「こうした方が良いはず」ではなく「数字で見る」こと**。
アクセス解析やSearch Consoleを見れば、ユーザーの行動は明確にわかります。
- どのページで離脱しているか
- どんな検索キーワードで来ているか
- どの導線がクリックされていないか
これらの“事実”をもとに改善を重ねることで、サイトは確実に変わっていきます。
思い込みではなく「データと意図」を軸にした改善が、中小企業サイトの成果を大きく左右します。
—